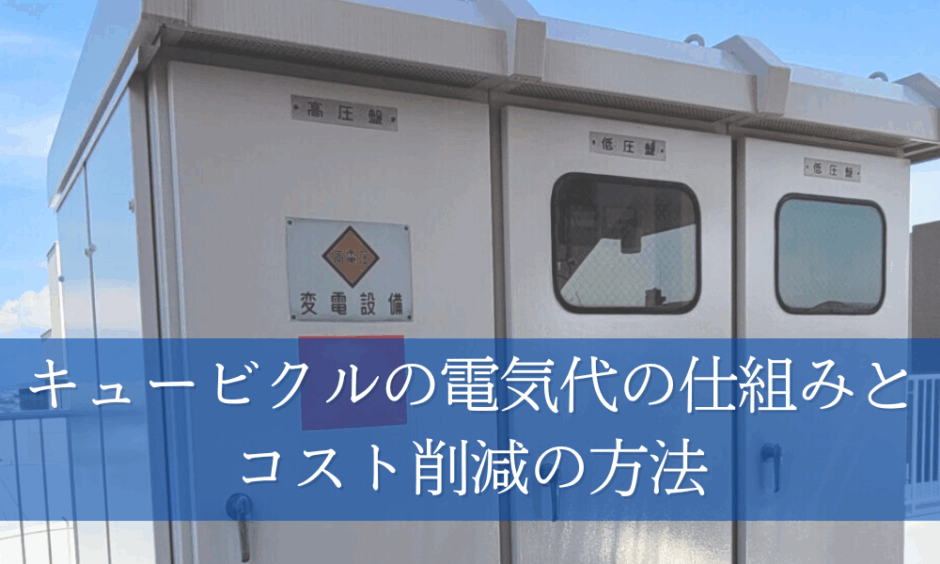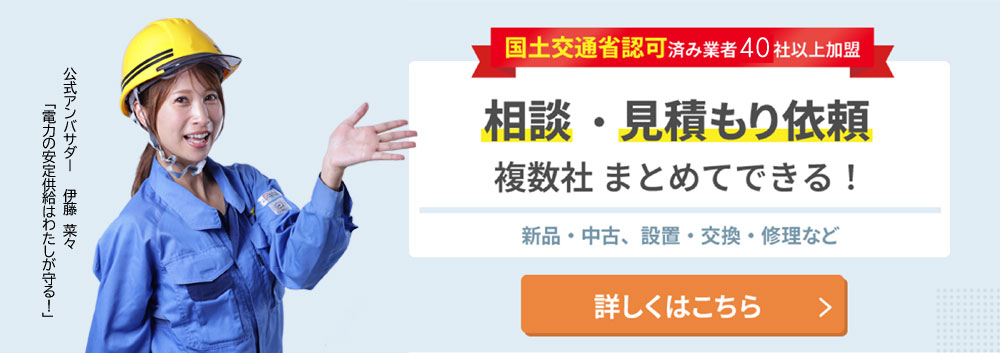近年、キュービクル(受変電設備)を設置している施設の管理者から「電気代が異常に高くなった」という声が急増しています。
電気代高騰には、複数の要因が複合的に影響しています。世界情勢による天然ガス・石炭価格の高騰、円安進行による輸入燃料費の上昇、そして再エネ賦課金の継続的な増加などです。
特にキュービクルを設置するような工場、病院、大型商業施設、オフィスビル、学校などは、大きな電力を使用します。そのため、月額電気代が数十万円から数百万円に達するケースも珍しくなくいのです。
このような状況下で、キュービクル施設の管理者は電気代の仕組みを正しく理解し、効果的なコスト削減策を講じることが急務となっています。適切な対策により、年間数百万円規模の削減も決して不可能ではありません。
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
キュービクルの電気代の考え方
キュービクルとは、高圧電力を安全に受電し、施設内で使用できる電圧に変換するための受変電設備です。正式には「キュービクル型高圧受電設備」と呼ばれ、電力会社から供給される6,600V(6.6kV)の高圧電力を、一般的な設備や機器で使用される200Vや100Vに変圧する重要な役割を担っています。
キュービクルの設置が必要となるのは、契約電力が50kW以上の施設です。具体的には以下のような施設が対象となります。
- 製造業の工場(小規模でも機械設備が多い場合)
- 大型商業施設(スーパーマーケット、ショッピングセンター)
- オフィスビル(中高層建築物)
- 病院・医療施設
- 学校・教育施設
- ホテル・宿泊施設
キュービクルを設置している施設は必然的に高圧受電契約を結ぶことになり、この契約形態が電気代の構造に大きな影響を与えます。
高圧契約では、一般家庭の低圧契約とは異なる料金体系が適用され、基本料金、電力量料金、各種調整費の算出方法も複雑になります。
キュービクルの電気代の内訳
それでは、キュービクルを設置している施設に適用される、高圧受電契約の電気料金について見てみましょう。キュービクルの電気代は、主に以下の4つの要素から構成されています。
- 基本料金
- 電力量料金
- 燃料費調整額
- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)
これら4つを合算して、毎月の電気代が計算されます。
基本料金の構造と影響
基本料金は契約電力(kW)に基本料金単価を乗じて算出され、電力を使用しなくても毎月固定で発生する料金です。
契約電力は過去1年間の最大デマンド値(30分間平均電力の最大値)を基準に自動的に設定されるため、一度でも大きな電力を使用すると、その後12ヶ月間は高い基本料金を支払い続けることになります。
また、基本料金は力率(電力使用の効率)によって、割引を受けることが可能です。そのため、キュービクル内に、力率を改善するためのコンデンサを設置します。
多くの施設では、基本料金が月額電気代の30~50%を占めており、最も重要な削減対象となります。
電力量料金と時間帯別料金
電力量料金は実際に使用した電力量(kWh)に応じて課金される料金です。一般的な契約では、全国的に使用電力量が多くなる夏季とその他の季節で単価が異なります。
また、昼間時間(8:00~22:00)と夜間時間(22:00~8:00)で異なる単価が設定されるプランも広く採用されており、昼間時間の方が高い料金となっています。この時間帯別の料金差を活用することで、電力使用タイミングの最適化による削減が可能です。
電力量料金は、使用した電力量に応じて決まるため、節電・省エネによって、直接的に削減することができます。
燃料費調整額・再エネ賦課金
燃料費調整額は、火力発電の燃料価格変動を電気代に反映させる制度です。原油・LNG・石炭の価格変動に応じて毎月調整される燃料費調整単価に使用電力を乗じて算出します。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)は、全ての電力使用者が負担する賦課金です。太陽光発電などの再エネ発電の普及に使用されます。
近年、これらの調整費が大幅に上昇しており、電気代高騰の主要因となっています。
キュービクルの電気代が高くなる原因
キュービクルの電気代が高くなってしまう主な原因を紹介します。
最大使用電力の偏りにる契約電力のアップ
キュービクル施設の電気代が高くなる最も一般的な原因は、契約電力が実際の使用実態に適合していないことです。設備増強や生産量拡大時に一時的に高いデマンドを記録した後、操業状況が変化したにも関わらず契約電力が高いまま維持されているケースが非常に多く見られます。
また、工場などでは、始業時の一斉稼働や昼休み明けの設備再稼働時にデマンド値がピークを迎える傾向があります。このようなピーク時の電力集中により、実際の平均的な電力需要よりもはるかに高い契約電力が設定されてしまい、基本料金の無駄な支払いが発生しています。
効率の悪い電気設備
効率の悪い電気設備を使用し続けることも電気代が高くなる要因です。近年の電気設備はどんどん省エネ性能が向上しており、10年前、20年前の設備と比べると同規模の電気設備でも使用電力が大きく下がることがあります。
特に、キュービクルの変圧器は、施設内で使用する電力のすべてを変換しているため、変圧器の効率は非常に重要です。そのため、省エネ法のトップランナー制度により、常に省エネ性能が向上しており、古い変圧器を最新の変圧器に変えるだけでも大きな省エネ効果があります。
老朽化した設備の継続使用は、無駄な電力消費により電力量料金が膨らむだけでなく、基本料金の押し上げにも繋がります。
長期間契約内容を見直していない
2000年3月からスタートした電力自由化により、キュービクルの受電契約も従来の地域電力会社だけでなく、新電力の様々なプランに切り替えられるようになりました。
しかし、電力自由化以降も、多くの施設で電気契約の見直しが行われていません。地域電力会社との従来契約を継続している施設では、市場競争による料金削減の恩恵を受けることができず、結果として高い電気代を支払い続けている可能性があります。
キュービクル設置工事の相場は?
設置・交換前に知っておきたい!
↓ ↓ ↓ ↓
キュービクルの工事費用
≫本体価格から納期まで
1番安い専門業者が見つかる
キュービクルの電気代を削減する方法
それでは、高いキュービクルの電気代を削減するにはどのようにすればよいでしょうか。ここで、多くの施設で適用できる主な削減方法を紹介します。
デマンド監視システムの導入
キュービクルにおける電気代削減の最も効果的な対策は、デマンド監視システムの導入です。リアルタイムで電力使用量を監視し、設定値に近づいた際にアラームを発生させることで、ピーク電力の発生を未然に防ぐことができます。
デマンド監視により、設備の一時停止や稼働時間の調整を行うことで、年間を通じて契約電力を抑制し、基本料金の大幅な削減が可能です。
稼働スケジュールの策定
大型の電気設備を同時に稼働させると、使用電力量が大きくなり、基本料金のアップにつながります。常時動かしている設備であれば仕方ありませんが、必要に応じて稼働させる大型の電気設備は、同時に稼働しないように工夫しましょう。
例えば、稼働スケジュールを策定し、同時に稼働しないようにするだけで、大幅な基本料金の削減が可能です。
高効率設備への更新による省エネ効果
既存設備の高効率化は、電力量料金とデマンド値の両方を削減する効果的な手段です。
キュービクルが古くなっている場合は、変圧器を最新のものに変えるだけでも大幅な改善が可能です。現在の変圧器は、20年前の変圧器に比べ、電力のロスが40~60%改善されています。
また、LED照明、高効率空調機、インバータ制御設備の導入など、電気設備全体の見直しによっても電気代削減が期待できます。
これらの設備更新は初期投資が必要ですが、政府や自治体の助成を受けられるケースも多いため、少ない負担で実施できる可能性があります。
新電力への契約変更
電力自由化により、キュービクルで受電している施設でも、地域電力会社以外の新電力事業者との契約が可能になりました。高圧契約における新電力の選択肢は豊富で、現在700社以上の小売電気事業者のうち、200社以上が高圧契約に対応しています。
新電力事業者では、地域電力会社よりも競争力のある料金設定を行っているケースが多く、大幅な電気代の削減が期待できます。また、固定単価プラン、市場連動型プラン、再生可能エネルギー比率の高いプランなど、多様な選択肢から施設の特性に最適なプランを選択できます。
新電力への切り替えに際して、キュービクルなどの受変電設備の変更は一切不要です。送配電網は既存のものを継続使用するため、電力の品質や供給安定性に変化はありません。切り替え手続きは基本的に書類手続きのみで完了し、工事や設備停止も不要なため、業務への影響を最小限に抑えて切り替えが可能です。
キュービクルにおける電気代見直しの重要性
キュービクルを設置するような施設では、使用する電気量も膨大で、電気代高騰の影響を大きく受けてしまいます。しかし、その分、適切な対策を講じることで得られる削減効果も大きく、年間数十~数百万円の削減ができるケースもあるのです。
デマンド監視の導入、運用方法の見直し、より省エネな設備への更新など、様々な対策により、電気代の削減を行うことが可能です。
新電力への切り替えは、設備投資を必要とせず、リスクも限定的でありながら、確実な削減効果が期待できる最も手軽な対策の一つです。電力自由化により与えられた選択権を活用し、施設の特性に最適な電力調達を実現することで、継続的なコスト削減と企業競争力の向上を図ることができます。
 高圧契約でも選べる!新電力の仕組み・料金比較・切り替え手順を徹底解説
高圧契約でも選べる!新電力の仕組み・料金比較・切り替え手順を徹底解説
 高圧電気料金はなぜ高い?料金の仕組みとコスト削減方法、新電力会社への切り替えポイントを解説
高圧電気料金はなぜ高い?料金の仕組みとコスト削減方法、新電力会社への切り替えポイントを解説
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓