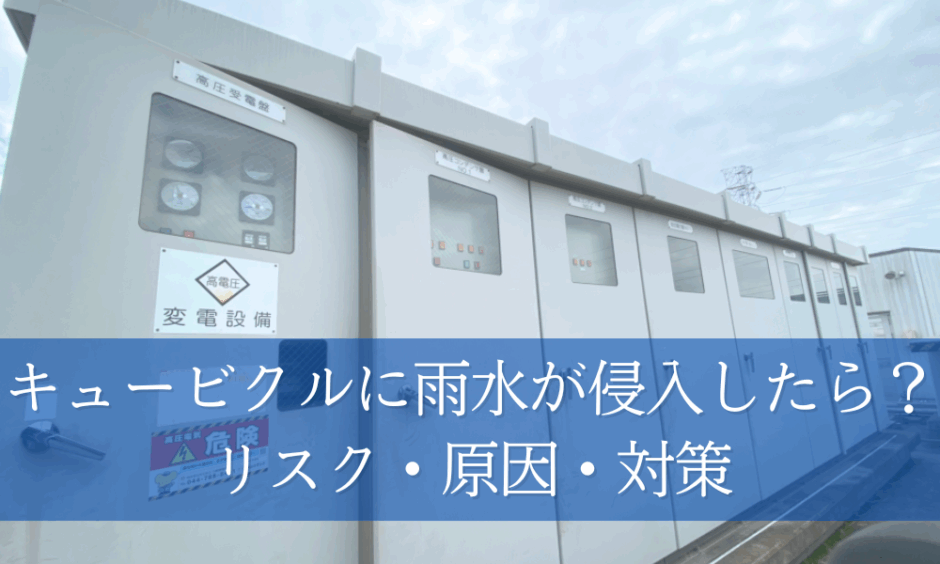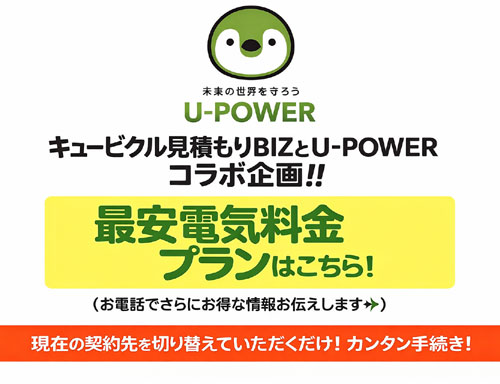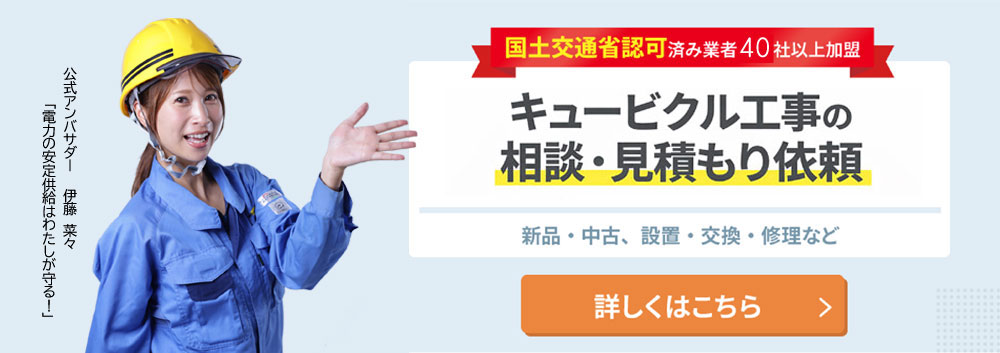工場やビル、商業施設などの電気設備として欠かせない「キュービクル」。高圧の電気を受電し、建物で使える電圧に変換する重要な役割を担っています。
しかし、大型の電気設備であるため、設置場所が問題になることも少なくありません。屋外の雨風や直射日光にさらされる環境に設置されることも多くあります。
そのため「キュービクルに雨水が侵入したらどうなるのか?」という不安を持つ方も多いのではないでしょうか。実際、雨水が内部に侵入すると、漏電や停電、さらには火災などの重大事故につながる可能性があり大変危険です。
この記事では、キュービクルに雨水が侵入するリスク、原因や対策、さらにトラブル発生時の対応方法について、初めての方にもわかりやすく解説していきます。
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
キュービクルに雨水が侵入するとどうなる?
キュービクルの内部には、変圧器や遮断器、開閉器など高電圧の電気を扱う機器が設置されています。本来は密閉構造によって外部環境から守られていますが、そこに雨水が侵入してしまうと深刻なトラブルにつながる恐れがあります。
絶縁性能の低下と漏電の危険
電気設備は電気を通さない素材による「絶縁」が確保されていることで安全に使えます。しかし、水は電気を通しやすいため、内部に水滴が付着すると絶縁性能が低下。結果として電気が漏れ出す「漏電」が発生し、停電や感電事故、設備の破損を引き起こす可能性があります。
特に短期的に大量の水が入り込んだ場合、水を通して電気が流れ出してしまうため、それまで機器に異常がなかったとしても、突然漏電が起こるため注意が必要です。
機器の腐食・劣化
雨水に含まれる不純物や湿気は、金属部分を腐食させる原因です。特に端子部分や銅バー、鉄製の部品はサビが進行しやすく、一度劣化すると交換や修理が必要になります。
これにより、本来の寿命よりも早く機器を更新せざるを得なくなるケースも少なくありません。
停電や火災のリスク
雨水が電気の流れる部分に直接触れると、本来電気が流れてはいけない経路に電気が流れる「短絡(ショート)」が起こることがあります。
短絡は一瞬で大量の電気が流れ、通常は遮断機などの保護装置の動作により停電が発生します。しかし、急激な短絡では、保護が間に合わず、設備が焼損し、最悪の場合は発火につながる可能性もあり、大変危険です。
施設全体の稼働が止まるだけでなく、人命にも関わる重大事故となりかねません。
波及事故・法的トラブルにつながる可能性
キュービクルは「電気事業法」に基づき、設置者に維持管理の義務があります。もし雨水侵入による事故が起きた場合、点検不足や管理不備とみなされる可能性も少なくありません。
施設内での感電や火災といった事故のリスクはもちろん、高圧受電では、施設内の事故が電力会社の設備に波及し、地域停電につながることもあります。地域停電が起きた場合、周囲の施設にも損害が出るため、社会的な責任を問われることになります。
このような事故では、需要家側が行政指導や損害賠償請求を受ける恐れもあるのです。
雨水侵入の主な原因
では、なぜキュービクルに雨水が入り込んでしまうのでしょうか。代表的な原因を見てみましょう。
経年劣化によるパッキンやシール材の損傷
屋外用キュービクルの扉や点検口、筐体の継ぎ目には、防水のためにゴムパッキンやシーリング材が使われています。
しかし、紫外線や温度変化によって劣化し、ひび割れや硬化が進むと防水性能が低下。そこから雨水が侵入するケースがよく見られます。
筐体の腐食・破損
キュービクルは、金属製の堅固な筐体に電気機器を納めた構造です。この筐体が経年劣化などで腐食し、穴が開いて雨水が侵入するケースがあります。また、外的な要因により破損し、雨水が入り込むケースも考えられます。
洪水による下部からの侵入
キュービクルは通常、コンクリート基礎の上に設置されます。もし基礎の高さが不十分だったり、周囲の排水が悪かったりすると、大雨で水たまりができて床面から浸水することがあります。
そのため、キュービクルの設置場所は水が溜まりにくい場所を選定し、基礎の高さは十分に確保することが大切です。
豪雨・強風による通気口などからの侵入
強風を伴う雨では、通気口などから水が吹き込むことがあります。
電気設備は熱を発するため、放熱の目的で通気口が設けられるのです。本来は内部に水が入らないよう設計されていますが、台風などの極端な気象条件では完全に防げない場合もあります。
工事での防水処理の不備
配線工事の際に、ケーブル引き込み口や配管接続部の処理が不十分だと隙間から雨水が侵入することがあります。
電力会社からの受電、施設側への送電のため、キュービクルには複数のケーブル・電線が接続されています。これらのケーブル・電線をキュービクルに入れ込む部分は、工事の際に防水処理を行い雨水が侵入しないようにしなければなりません。
しかし、施工手順を守っていなかったり、シール材の重点不足などのミスがあったりと、施工の不備があると、適切な防水性能が発揮されず雨水が入り込む原因となります。
また、当初の施工が適切でも、その後の経年で劣化しやすい部分でもあるため、注意が必要です。
雨水侵入の点検方法
雨水の影響を早期に発見するには、定期点検でのチェックが欠かせません。具体的にチェックすべきポイントは以下の通りです。
- 内部の目視確認:水滴や湿気、サビがないか確認
- 扉やパッキンの状態:ゴムが硬化していないか、破損がないか
- 床面や基礎部分:浸水や水たまりができていないか
- 絶縁抵抗測定:絶縁性能が低下している場合は、雨水侵入が原因の可能性がある
キュービクルは、法令により月次・年次の点検が義務付けられているため、その際に雨水の侵入を忘れず確認するようにしましょう。また、台風や豪雨の後には臨時点検を行うことも推奨されます。
高圧電力の操作は資格がなければ行うことはできません。そのため実際の点検は電気主任技術者が行うことになります。
契約している点検項目や点検報告書で、雨水の侵入も対応できているか確認しておくとよいでしょう。
キュービクル設置工事の相場は?
設置・交換前に知っておきたい!
↓ ↓ ↓ ↓
キュービクルの工事費用
≫本体価格から納期まで
1番安い専門業者が見つかる
雨水侵入を防ぐための対策
雨水侵入によるトラブルを未然に防ぐには、設置時に雨水が入りにくい構造・条件を満たすことが重要です。また、定期点検やメンテナンスによる対応も忘れてはなりません。
防水性能の高いキュービクルを選定する
屋外に設置する場合は、屋外用のキュービクルを選定します。屋外用のキュービクルはIP43以上の防水・防塵性能を備えています。
しかし、一言で屋外用と言っても、実際の防水性能は製品により異なります。長く使いたいのであれば、防水性能についてしっかりと確認しておくことが大切です。
また、塩害地域であれば、通常よりも腐食しにくいステンレス製や溶融亜鉛メッキ製を選定するなど、環境に合わせた対応が求められます。
雨風の影響を受けにくい場所に設置する
屋外に設置する場合でも、建物の陰などできるだけ雨風の直撃を避けられる場所を選びます。また、下部からの雨水侵入が起こらないよう、水が溜まりやすい場所は避けなければなりません。
適切な設置場所がない場合は、庇を設けたり、フェンスや防風ネットで囲ったりと、直接の雨風を防ぐ工夫も有効です。
シール材・パッキンの定期交換
ゴムやシーリング材は数年で劣化が進むため、定期的に交換することが重要です。
雨水侵入により、漏電や短絡といった事故が起きると、大きな損害が発生します。一方でシール材やパッキンは安価なため、大きなコストをかけずに対策が可能です。
点検時にひび割れを見つけたら早めに対処しましょう。
雨水侵入トラブルが発生した場合の対応
もし実際に雨水が侵入している、あるいはその疑いがあることに気づいたら、次のように対応しましょう。
1.自己判断で触らない
高圧設備は非常に危険です。内部を拭いたり、扉を開けっぱなしにして乾かそうとしたりする行為は感電のリスクがあるため絶対に避けてください。
2.電気主任技術者や専門業者に連絡
まずは契約している電気主任技術者に報告し、必要に応じて緊急点検を依頼します。
3.修理・部品交換の実施
パッキン交換やシール材充填など軽微な修理で済む場合もあれば、変圧器や遮断器の交換が必要になるケースもあります。費用は数万円から数十万円と幅広く、被害の程度によって異なります。また、状況によってはキュービクル全体の交換が推奨される場合もあります。
4.保険の活用
火災保険や動産保険で補償される場合もあります。また、省エネ更新や防災強化に伴う補助金制度を活用できるケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
キュービクルは高圧の電気が流れているため、資格を持っていない人が操作したり、稼働中に内部に触れたりすると大変危険です。とにかく自己判断での対応は避け、速やかに電気主任技術者に連絡するようにしましょう。
修理で済むケースと交換が必要なケース
雨水侵入が確認された場合、軽微なものであれば修理で対応できますが、場合によってはキュービクルごと交換する必要もあります。
修理で済むケース
以下のような軽微な修理であれば、キュービクル全体の交換は必要ありません。
- 扉のパッキンやシール材の交換
- ケーブル引き込み口の防水処理のやり直し
- 部分的な端子やブレーカーの交換
これらは数万円〜数十万円程度で対応できる場合が多いです。
しかし、対応年数を大幅に超えている場合など、キュービクルの更新が望ましい場合もあります。そのため、電気主任技術者の意見も聞きながら総合的に判断することが望ましいでしょう。
交換が必要なケース
以下の状況であれば、キュービクルごと交換することを検討しましょう。
- 筐体に穴が開いている
- 変圧器や遮断器など主要機器が広範囲で腐食している
- 内部で絶縁不良やショートが頻発している
- 設置から20年以上経過している(老朽化が進んでいる)
- 事故防止のため電気主任技術者から更新を強く推奨された
キュービクル全体を更新する場合、必要な費用は数百~数千万円と高額になります。価格は電気容量や設置環境により大きく異なるため、専門業者による見積もりが必要です。
キュービクルの更新では、複数の業者に見積もりを取り、信頼できる業者を選定することが求められます。
雨水侵入はキュービクルの一大危機
キュービクルにおける雨水侵入は、軽微に見えて重大な事故の引き金となるリスクを抱えています。
雨水が入ると「漏電」「腐食」「停電・火災」の原因となり、事業の停止や機器の故障により大きな損害が発生するリスクがあります。そればかりか、死亡事故や波及事故により、大きな社会的責任を問われることにもなりかねません。
施設の安全と安定稼働を守るためにも、キュービクルの雨水対策は欠かせません。早めの点検と対策で、安心して設備を運用していきましょう。
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓