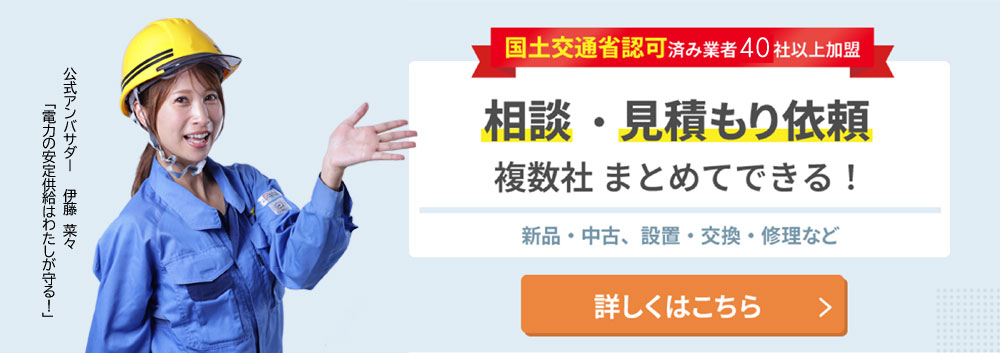近年、工場や大型店舗、オフィスビルなどの高圧受電契約を結んでいる企業から「電気代が高すぎる」という声が増えています。特に、2022年以降の電気料金高騰は深刻な問題となっており、企業の経営を圧迫している状況です。
キュービクル(高圧受電設備)を設置している工場、大型商業施設、病院、学校などでは、電気使用量も大きいため、月額数十万円から数百万円の電気料金を支払っているケースも珍しくありません。
本記事では、高圧電気料金がなぜ高いのか、その仕組みを詳しく解説するとともに、具体的なコスト削減方法や新電力への切り替えによる削減効果について、わかりやすくご説明します。
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
高圧電気料金の仕組み
まずは、基本的な情報として、高圧受電契約での電気料金の仕組みについて説明します。
高圧契約の基本的な料金構成
高圧契約の電気料金は、主に以下の2つの要素から構成されています。
- 基本料金・・・毎月固定の金額
- 電力量料金(従量料金)・・・使用した電力量に応じて金額が決定
また、従量料金に火力発電の燃料価格変動を電気料金に反映させるため、燃料調整費という制度があり、原油・LNG・石炭の価格変動に応じて毎月調整されます。
さらに、再エネ賦課金といって、再生可能エネルギーの導入促進を目的とし、全ての電力使用者が負担する賦課金でも加算されます。
基本料金の仕組み
基本料金は、契約電力(kW)に単価を掛けた金額で算出されます。電力を実際に使用しなくても毎月固定で発生する料金です。
契約電力は、過去1年間の最大使用電力量(30分間の平均使用電力の最大値)を基準に設定されます。そのため、一度高い使用電力量を記録すると、その後1年間は高い基本料金を支払い続けることになるのです。
また、力率(電気設備の効率)によって割引を受けることができるため、キュービクルに力率改善のためのコンデンサを設置するといった対策が取られます。
電力量料金の仕組みと時間帯別制度
電力量料金(従量料金)は、実際に使用した電力量(kWh)に応じて変動する料金です。使用電力量にあらかじめ定めた単価を乗じて計算します。
高圧契約では、夏季(7月~9月)とその他の時期で単価が異なります。夏季は電気の需要が高まるため、他の時期に比べて高く設定されているのです。
また、使用時間帯によって単価が異なる「時間帯別料金制度」も存在します。昼間時間と夜間時間で単価が分けられているため、電力使用のタイミングを工夫することで料金削減が可能です。
燃料調整費
燃料調整費は、火力発電の燃料価格変動を電気料金に反映させる制度です。原油・LNG・石炭の価格変動に応じて毎月調整されます。
電力量料金と同じく、使用した電力量に毎月決定する単価を乗じて計算します。近年は燃料調整費が高止まりしており、電気料金高騰の主要因です。
再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)
再エネ賦課金は、再生可能エネルギーの導入促進を目的として、全ての電力使用者が負担する賦課金です。徴収された賦課金は国の指定機関を通じて再エネ発電事業者への買取り費用に充当されます。
再エネ賦課金の額は、法令等に基づいて定められるため、原則として電力会社や契約プランによる差はありません。
再エネ賦課金も年々上昇傾向にあり、電気料金値上げの要因となっています。
高圧電気料金が「高い」主な理由
多くの企業が高圧電気料金の高さを実感している背景には、近年の急激な料金上昇があります。2020年と比較して、2023年の電気料金は地域や契約内容によって20~40%程度上昇しており、これは企業経営に深刻な影響を与える水準です。
この料金上昇の最大の要因は、燃料費調整費の大幅な上昇です。世界的な天然ガスや石炭価格の高騰により、火力発電のコストが大幅に増加しました。また、円安の進行により輸入燃料の調達コストがさらに押し上げられ、燃料調整費は過去に例を見ない水準まで上昇しています。
さらに、再エネ賦課金も継続的に増加傾向にあります。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、この賦課金は年々上昇しており、特に電力使用量の多い高圧契約の施設では、その影響が顕著に現れています。
基本料金に関しても、多くの企業で見直しが適切に行われていない現状があります。デマンド管理が不十分な場合、不必要なピーク電力が発生し、翌月以降の契約電力(基本料金)を押し上げる原因となっています。
電力市場の制度変更も料金上昇の一因です。電力の自由化以降、市場価格の変動が料金により直接的に反映される仕組みが導入され、需給バランスの変化が料金に与える影響が大きくなっています。特に夏季や冬季の需要ピーク時には、市場価格が高騰し、それが電気料金に反映される構造になっています。
高圧電気料金の削減対策
高い高圧電気料金を削減するには、基本料金と電力量料金を下げる対策が有効です。ここで基本的な対策を紹介します。
デマンド監視・ピークカットの実施
高圧契約の基本料金は、直近12カ月の最大使用電力の中で、最も高い値となります。そのため、一時的に大電力を消費すると、翌月から1年間にわたって高い基本料金を支払うことになるのです。
そこで、デマンド監視・ピークカットの実施は、最も効果的な対策の一つと言えます。デマンド監視装置を導入し、電力使用量をリアルタイムで監視することで、ピーク電力の発生を未然に防ぐのです。
設定した上限値に近づいた際にアラームを発生させ、一時的に不要な設備を停止することで、年間を通じて基本料金を抑制できます。高度なデマンドシステムの中には、自動で電力消費を抑制するものもあるため、導入にあたってはどのようなデマンドシステムが適しているか、しっかりと検討しましょう。
デマンド監視・ピークカットの実施だけで年間数十万円から数百万円の削減効果が期待できる場合があります。
省エネ・高効率設備への更新
使用電力量を削減するためには、電気設備の省エネ・高効率化も重要です。
例えば、キュービクルの変圧器を高効率な製品に更新したり、既存の蛍光灯や水銀灯をLED照明に交換したりといった対策で、使用電力量が削減できます。
これらの更新は初期コストが発生しますが、電気料金削減効果により長期的にはコストが回収できる場合も多いでしょう。イニシャルコストとランニングコストのバランスを考えながら、検討することが重要です。
運用改善による電力削減
電気設備の運用方法の見直しにより無駄な電力使用を削減できます。
空調の設定温度適正化、不要時間帯の自動停止設定、設備の稼働スケジュール最適化などにより、電力使用量を削減できる場合があります。また、夜間電力の有効活用により、昼間時間の高い電力量料金を避けることも効果的です。
人的な工夫だけでは、使用電力量の削減はなかなか難しいものです。運用ルールの策定や機械的な自動化など、運用方法を工夫することが重要です。
データ分析による最適化
ここまで、基本的な対策を紹介しましたが、どういった対策が効果的かは、施設ごとの運用状況によって大きく異なります。そのため、電力使用データの分析は、削減対策の効果を最大化するために不可欠です。
スマートメーターや電力測定装置により詳細な使用データを収集し、時間帯別、設備別の電力使用パターンを把握することで、より具体的で効果的な削減策を立案できます。データ分析により予想以上の無駄な電力使用が発見されるケースも少なくありません。
キュービクル設置工事の相場は?
設置・交換前に知っておきたい!
↓ ↓ ↓ ↓
キュービクルの工事費用
≫本体価格から納期まで
1番安い専門業者が見つかる
「新電力」による電気料金削減
電力自由化により、高圧契約でも地域の大手電力会社以外の「新電力」(PPS:電力小売事業者)を選択できるようになりました。この制度変更は、企業にとって電気料金削減の大きなチャンスとなっています。
新電力の基本的な概要
新電力とは、電気事業法に基づく小売電気事業者の許可を得て電力販売を行う事業者のことです。従来の地域電力会社(東京電力、関西電力など)とは異なる料金体系やサービスを提供しており、顧客のニーズに応じた柔軟なプランが用意されています。
地域電力会社と新電力の最大の違いは、料金設定の自由度です。地域電力会社は規制料金として一律の料金体系を採用していますが、新電力は市場競争により独自の料金体系を設定できます。この結果、使用パターンや契約規模に応じてより有利な料金プランを選択できる可能性があります。
電力品質と安定性の担保
電力自由化により、契約先を変更しても送配電網は既存のものを使用するため、電力の品質や安定性に変化はありません。停電リスクが増加することもなく、万が一契約した新電力事業者が事業を停止した場合でも、地域電力会社による「最終保障供給」により電力供給が継続されます。
高圧契約での導入実績
高圧契約での新電力利用実績も豊富で、製造業の工場、大型商業施設、病院、学校、オフィスビルなど様々な業種で導入が進んでいます。
特に電力使用量が多い施設ほど削減効果が大きくなる傾向があり、年間数百万円から数千万円の削減実績を持つ企業も少なくありません。
高圧契約の新電力のメリット・デメリット
高圧新電力への切り替えには明確なメリットがある一方で、理解しておくべきデメリットやリスクも存在します。
新電力の主なメリット
新電力には様々なメリットがあります。
- コスト削減効果
- プランの柔軟性
- 環境対応の価値
メリットの筆頭は、やはりコスト削減効果です。電力使用量年間100万kWh以上の施設では、年間数百万円から数千万円の削減事例も珍しくありません。特に電力集約的な製造業や、24時間稼働の施設では削減効果が顕著に現れます。また、従来の画一的な料金体系ではなく、企業の使用パターンに最適化されたプランを選択できるため、効率的な電力調達が可能になります。
プランの柔軟性も大きなメリットです。企業のニーズに応じた多様な選択肢があり、プランのカスタマイズや契約内容の調整が可能な場合もあります。また、契約電力の見直しやデマンド管理のコンサルティングサービスも併せて利用することで、総合的なエネルギーコストの最適化が図れます。
環境対応の側面では、再生可能エネルギー由来の電力を積極的に調達することで、企業のカーボンニュートラル目標達成に直接的に貢献できます。これは単なるコスト削減を超えて、企業価値の向上や社会的責任の履行という観点から重要な意義を持ちます。
新電力の主なデメリット
新電力には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
- 価格変動リスク
- 供給停止リスク
デメリットとして最も注意すべきは、市場連動型プランにおける価格変動リスクです。電力卸売市場の価格は需給バランスにより大きく変動するため、需要がひっ迫する時期には従来の料金を上回る可能性があります。過去に市場連動型プランを選択していた需要家で高額な電気料金が発生した事例もありました。
新電力には様々なプランがあり、市場連動型以外のプランや、価格高騰時の上限価格が設定されているものもあります。通常時のコストとリスクのバランスを考えてプランを選択しましょう。
また、新電力事業者の供給停止リスクも考慮すべき要素です。事業の継続性に不安のある事業者を選択した場合、供給停止により契約が強制的に解除される可能性があります。ただし、このような場合でも地域電力会社による「最終保障供給」により電力供給は継続されるため、停電リスクはありません。
高圧電気料金が高いと思ったら
高圧電気料金の高騰は多くの企業が直面している深刻な問題ですが、適切な対策により確実に削減効果を得ることができます。まず重要なのは現状把握です。自社の電力使用パターンと料金構造を詳細に分析することで、最適な削減策を立案できます。
社内対策として、デマンド管理の徹底、高効率設備への更新、運用改善などは、投資対効果の高い確実な方法です。これらの対策と並行して、新電力への切り替えを検討することで、さらに大きな削減効果が期待できます。
新電力の利用は、電力自由化により与えられた企業の権利です。リスクは限定的で、切り替え手続きも簡単です。まずは複数の新電力事業者から提案を受け、現在の料金との比較検討を行う価値は十分にあります。
電気料金の見直しは一度実施すれば継続的な効果が得られる投資です。エネルギーコストの最適化により、本業への投資資金を確保し、企業競争力の向上に繋げることができます。電気料金が高騰を続けている今こそ、電気料金の抜本的な見直しを実行すべき時期と言えるでしょう。
 高圧契約でも選べる!新電力の仕組み・料金比較・切り替え手順を徹底解説
高圧契約でも選べる!新電力の仕組み・料金比較・切り替え手順を徹底解説
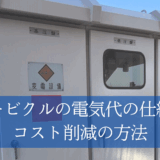 キュービクルの電気代が高い?電気代の仕組みとコスト削減の方法
キュービクルの電気代が高い?電気代の仕組みとコスト削減の方法
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓