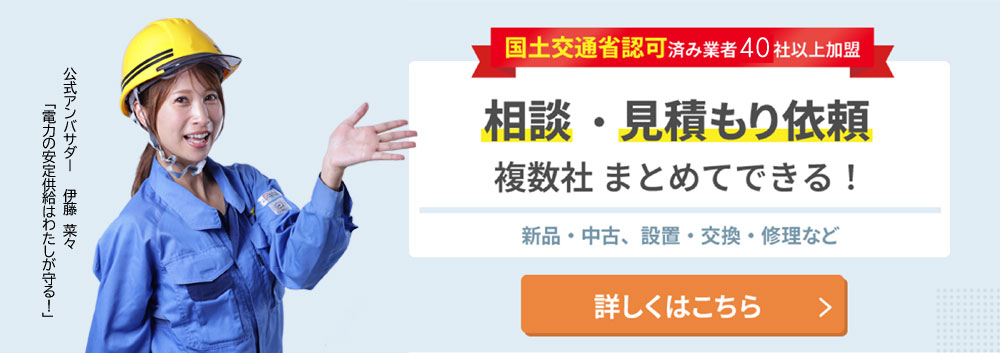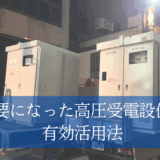一般家庭向けの電力自由化については広く知られています。しかし、実は高圧受電契約についてはそれ以前の2000年から段階的に自由化が進められており、現在では豊富な選択肢が用意されています。
それにも関わらず、多くの企業の管理担当者が「高圧契約でも新電力を選べる」という事実を十分に認識していないのが現状です。特に中小企業では、従来通り地域の大手電力会社との契約を継続しており、新電力への切り替えを検討したことがない企業が大半を占めています。
近年、燃料費調整費の上昇や再生可能エネルギー発電促進賦課金の増加により、多くの企業で電気代が経営を圧迫する水準まで上昇しています。このような状況下で、従来の料金体系とは異なるアプローチを提供する新電力が、電気代削減の手段として注目を集めているのです。
本記事では、新電力の基本的な仕組みから具体的な切り替え手順まで解説します。
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
目次
高圧契約における新電力とは?
新電力とは、電気事業法に基づく小売電気事業者の登録を受けて、電力の小売事業を行う事業者のことです。2000年3月から段階的に開始された電力自由化により誕生しました。
現在では、従来の大手電力会社(東京電力、関西電力など)以外にも、多くの事業者が独自の料金体系やサービスで電力を販売しています。
既存の高圧契約を新電力に切り替えることで大幅な電気料金削減が可能です。そのため、すでに多くの事業者が新電力に契約変更を行っています。
新電力と従来の地域電力会社との違い
従来の地域電力会社との最大の違いは、発電と販売の分離にあります。電力自由化により、地域電力会社は、発電・送電・小売りの3つに分離されました。新電力は、このうち小売り部分を担っています。
新電力会社の多くは自社で大規模な発電設備・送電設備を持たず、卸電力取引所(JEPX)からの電力調達や、独立系発電事業者からの電力購入により必要な電力を確保します。この仕組みにより、発電設備への巨額投資を必要とせず、より柔軟で競争力のある料金設定が可能なのです。
高圧契約向け新電力の特徴
高圧契約に対応する新電力の特徴は、法人向けに特化したプランの豊富さです。一般家庭向けの低圧契約とは異なり、高圧契約では企業ごとの電力使用パターンが大きく異なるため、個別のニーズに対応したカスタマイズ性の高いプランが提供されています。
製造業、商業施設、病院、学校など、業種別の特性を考慮した料金体系や、使用量規模に応じた段階的な割引制度なども充実しています。
付加サービスの充実
事業者向けの新電力では専門的なコンサルティングサービスを提供する事業者も多く存在します。電力使用データの分析、デマンド管理の提案、省エネ設備導入のアドバイスなど、単なる電力供給にとどまらない総合的なエネルギーソリューションを提供している点も大きな特徴です。
現在、日本全国で700社以上の小売電気事業者が登録されており、その中でも高圧契約に対応する事業者は200社以上に上ります。
高圧契約における新電力の料金体系と比較方法
新電力への切り替えを検討するには、料金体系を理解して、実際にかかる電気料金を比較する必要があります。
基本的な料金構成
高圧契約の料金は基本的に「基本料金」「電力量料金」「燃料調整費」「再生可能エネルギー発電促進賦課金」から構成されます。
基本料金は契約電力に応じて、電気を使用しなくても発生する料金です。電力量料金は、実際の使用電力量に料金単価を乗じて計算します。
地域電力会社等が使用している一般的な計算式は以下の通りです。
- 電気料金=基本料金+電力量料金+再生可能エネルギー発電促進賦課金
- 基本料金=料金単価 × 契約電力 × (185 – 力率) / 100
- 電力量料金=料金単価 × 使用電力量 + 燃料費等調整額
ただし、新電力では、様々な契約プランがあるため、新電力各社で算出方法や設定が異なることがあります。
新電力の豊富な契約プラン
現在の電力契約と新電力の電気料金を比較する場合、主に基本料金と電力量料金を比較することになります。しかし、新電力では様々な契約プランが存在するため、単純な料金単価の比較ができるとは限りません。
契約電力の算出も新電力各社で取り扱いが異なります。従来の地域電力会社では過去1年間の最大使用電力に基づいて契約電力が自動的に設定されますが、新電力では各社で設定方法が異なり、最大使用電力に応じて毎月基本料金が変動するプランも存在します。
また、電力量料金においても、季節別・時間帯別の料金単価の設定、電力卸売市場の価格に連動するなど様々なプランがあります。
このため、電気料金を比較するには、現在の電気の使用状況を確認し、検討対象の契約プランで料金を計算し直して、同じ条件で比較するようにしましょう。
見積もりの取得と比較のポイント
契約プランごとの電気料金を比較するには、実際の使用料を元に各プランの電気料金を計算して比較する必要があります。しかし、電気料金の計算は意外と複雑です。そこで、新電力に見積もりを依頼する方法があります。
見積もり比較を行う際のポイントは、単価だけでなく契約期間、解約条件、再エネ比率なども総合的に評価することです。
特に市場連動型プランの場合は、過去の市場価格データに基づく試算結果と、価格変動リスクの上限設定の有無は必ず確認するようにしましょう。上限設定がないと、価格高騰時に高額な請求を受けるリスクがあります。
また、燃料調整費の取り扱い方法、賦課金の計算方法、力率割引の適用条件なども事業者により異なるため、詳細な比較検討が必要です。
キュービクル設置工事の相場は?
設置・交換前に知っておきたい!
↓ ↓ ↓ ↓
キュービクルの工事費用
≫本体価格から納期まで
1番安い専門業者が見つかる
新電力を活用した高圧電気料金削減のメリット
新電力を活用した高圧電気料金の削減には様々なメリットがあります。ここで、主なメリットを紹介します。
単価面での優位性とプランの多様性
新電力は、既存の地域電力会社のプランよりも安い基本料金や電力量料金の単価を設定することで、顧客を確保しています。そのため、地域電力会社より安い料金設定の事業者が多く存在します。
さらに、電力卸売市場(JEPX)の価格に連動した料金体系である、市場連動型プランもあります。電力卸売価格の高騰により、高額な電気料金となるリスクを負う代わりに、通常時はより安価に電気を使用できるプランです。
料金削減メリットは、単価の優位性だけでなく、多面的な効果が期待できます。従来よりも細かい時間帯別料金や、基本料金が安価な代わりに電力量料金が高いなど、様々なプランを選択することが可能です。これらの多様なプランは、電気の使用状況によって大きな電気料金削減となります。
契約内容の柔軟性とカスタマイズ
契約内容の柔軟性も大きなメリットです。
地域電力会社では、多くの顧客に対応するため一律のサービスとなり、契約内容の個別調整などは一切できません。しかし、新電力の事業用のプランでは事前の協議によって細かい調整が可能です。
新電力事業者は顧客の使用パターンに応じて契約電力の調整、料金体系のカスタマイズ、請求書の詳細化など、きめ細かなサービスを受けられる可能性があります。
環境配慮とCSR効果
再生可能エネルギーを使用した電力プランによる環境配慮とCSR効果も、企業にとって重要な価値となっています。
新電力事業者の中には、太陽光、風力、水力、バイオマスなどの再エネ由来電力の比率を高めたプランを提供している事業者が数多く存在します。これらのプランを選択することで、企業のCO2排出量削減目標の達成や、ESG経営の推進に直接的に貢献できます。
エネルギー管理の高度化
新電力の中には、請求書の詳細化や使用量データの可視化など、エネルギー管理の高度化を支援するサービスを提供しているところもあります。
時間帯別、設備別の詳細な使用データを提供することで、より精密なエネルギー管理と削減対策の立案が可能になります。また、それらのデータを活用した電力コンサルを受けられる場合もあります。
新電力を活用した高圧電気料金削減のデメリット
新電力には、メリットだけでなくデメリットも存在します。新電力を検討する上でデメリットを把握しておくことは重要です。
電気料金高騰による高額な請求のリスク
新電力会社の市場連動型プランでは、急激な電力卸売価格の高騰により、従来の地域電力会社のプランよりも高額な電気料金を請求されるリスクがあります。
価格高騰のリスクは、新電力会社の規約やプランによって異なるため、契約内容を事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
また、今後、地域電力会社においても、高圧契約の従来プランは廃止となり、市場連動プランが標準となる予定です。そうなれば、既存のプランのままでも同様のリスクを負うことになります。
リスク回避の面からも地域電力会社や主要な新電力の料金プランを把握しておくことが重要になっていくでしょう。
契約期間の設定
通常、電力契約は需要家側の申し入れにより、随時解約することが可能です。しかし、新電力のプランでは、契約期間が定められているものが少なくありません。
契約期間中の解約は違約金が発生するため、電力契約が不要になった場合に不要なコストが発生します。また、別の電力会社に契約を変えたい場合も、契約変更の時期を調整しなければならないなどの制限が発生します。
契約中の新電力会社の撤退
契約中の新電力が撤退することにより、高圧契約が廃止されてしまうことがあります。
新電力側の事情で契約を廃止する場合には、事前の通知期間が定められていますが、高圧契約では契約切り替えに必要な期間もあるため、早急に契約先を決めて手続きを行わなければなりません。また、新電力が破産等により、急遽契約がなくなってしまうこともあります。
その様な緊急事態でも「最終保障供給」により地域電力会社が電力供給を続けることが定められており、いきなり停電になることはありません。実際に、最終保障供給によって電力供給を受けている例も存在します。
しかし、最終保証供給における電気料金は、地域電力会社が定めた料金プランが適用されるため、通常よりも高額な電気料金となる恐れがあります。
削減効果に影響する要因
削減効果の大きさは以下の要因に大きく依存します。
- 電力使用量の規模
- 使用時間帯の特性
- 契約電力の適正性
- 市場価格の動向
まず、年間の電力使用量が多いほど、スケールメリットによる削減効果が大きくなります。新電力との単価交渉でも、電力使用量が多いほど有利になるでしょう。
また、夜間や休日の使用比率が高い施設ほど、時間帯別料金の恩恵を受けやすくなります。新電力では、時間帯や曜日別の料金プランも豊富なため、使用状況に応じたプランを選択することが重要です。
現在の契約電力が実際の使用状況に対して過大に設定されている場合、見直しによる基本料金削減効果が大きくなります。従来の地域電力会社では、一度大きな電力を使用すると、その後12ヶ月間はその最大電力が契約電力になります。しかし、新電力では、契約電力の決め方も各新電力によって異なるため、柔軟な対応が可能です。
市場連動型プランの場合、電力卸売市場の価格動向により削減効果が変動します。ユーザー側で調整できないため、リスクでもあります。
高圧契約を新電力に切り替える流れ
高圧新電力への切り替えは、適切な手順を踏むことで円滑に進めることができます。一般的な切り替えの流れを段階的に説明します。
Step1:現在の契約状況・電力使用状況の確認
現在の契約確認が最初のステップです。現在契約している地域電力会社からの請求書や契約書類を準備し、契約種別(高圧A、高圧B等)、契約電力、料金メニュー、年間電力使用量、月別使用量の推移、デマンド値の推移などの基本情報を整理します。
また、現在の契約に解約予告期間や違約金の設定がないかも確認しておきましょう。違約金が発生すると、せっかく安価な料金プランに変更しても、全体として損失になる可能性があります。
Step2:複数社からの見積取得
検討したい新電力から、料金プランの詳細や契約後の電気料金のシミュレーションなどを作成してもらいます。
これらの見積もり資料は、複数社に依頼し、比較検討すると効果的です。各社に同じ条件で見積もりを依頼し、料金水準だけでなく、契約条件、サービス内容、事業者の信頼性も含めて総合的に比較しましょう。
見積もり取得の際は、必ずStep1で確認した詳細な電力使用データを提供し、精度の高いシミュレーションを実施してもらうことが重要です。
Step3:契約手続きの実施
電力の購入先が変わるといっても、工事や現地での作業は基本的に必要ありません。新電力が担当するのは電力の販売のみであり、送電は従来の地域電力会社が担当するためです。
そのため、契約手続きは書類手続きのみで完了します。新電力の事業者との間で電力供給契約を締結し、現在の地域電力会社に対しては解約手続きを行います。多くの場合、新電力の事業者が解約手続きを代行してくれるため、手続きの負担は最小限に抑えられます。
Step4:切り替え完了までの期間
新電力への切り替え手続きには通常1~3ヶ月程度の期間が必要です。この期間中も電力供給は継続されるため、業務への影響はありません。
切り替え日には電力メーターの検針が必要で、事前に新電力事業者から詳細なスケジュールが通知されます。ただし、最近では遠隔で電力量を計測できるスマートメーターが一般的になっているため、現地での作業は一切ない場合もあります。
Step5:切り替え後の請求・検針について
切り替え後の請求書は新電力事業者から発行され、支払い先も新電力事業者となります。検針業務は従来通り地域の送配電事業者が実施しますが、何かあったときに問い合わせ対応を行う窓口は新電力です。
多くの新電力事業者では、WEBサイトでの使用量照会サービスや、詳細な使用データのレポート提供なども行っており、エネルギー管理の高度化に役立ちます。
まずは新電力で高圧電気料金の比較をしてみよう!
高圧契約の新電力への切り替えは、電気料金の削減と企業の持続可能な経営を両立できる有効な選択肢です。電力自由化により与えられた選択権を活用することで、従来の画一的な料金体系から脱却し、企業の特性に最適化されたエネルギー調達が可能になります。
エネルギーコストの最適化は企業競争力の向上に直結する重要な経営課題であり、新電力はその実現のための有力な手段といえるでしょう。
料金比較だけであれば何らリスクはありません。まずは一度新電力の料金プランを確認して、現在の電気料金と比較してみましょう。
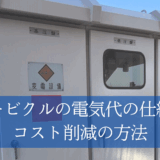 キュービクルの電気代が高い?電気代の仕組みとコスト削減の方法
キュービクルの電気代が高い?電気代の仕組みとコスト削減の方法
 高圧電気料金はなぜ高い?料金の仕組みとコスト削減方法、新電力会社への切り替えポイントを解説
高圧電気料金はなぜ高い?料金の仕組みとコスト削減方法、新電力会社への切り替えポイントを解説
国土交通省認可済みの専門業者が加盟している「キュービクル専門の総合サイト」です。
簡単なフォームに入力をするだけで、対応地域の加盟企業が見積もりや相談に答えてくれます!

「今、見積もっているキュービクル本体だけをもっと安くしたい」などもご相談ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓